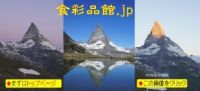「はじめましてあおさのりです」渥美半島たはらブランド認定。ヒトエグサ科(細胞層が1層)とアオサ科(細胞層が2層)の違い。「あおさ」と「アオサ」。アナアオサ,スジアオノリ,ウスバアオノリとは。そして購入したエーコープあいち桜町店が閉店します
「あおさ」あるいは「あおさのり」、「青ばら」と呼ばれている海藻について、
・アオサ目ヒトエグサ属ヒトエグサと一般的には紹介されることが多い。
あおさ出荷の全国第一位である主産地の三重県水産研究所によると、
・アオサ藻網ヒビミドロ目ヒトエグサ科(細胞層が1層)ヒトエグサ属ヒトエグサ(地方名あおさ)

そして、
・アオサ目アオサ科(細胞層が2層)アオサ属アナアオサなど
・アオサ目アオサ科(細胞層が2層)アオノリ属スジアオノリ,ウスバアオノリなど

と紹介されている。
上記のうち、三重県では細胞層が1層のヒトエグサを養殖し、「あおさ」として出荷していることに対して、愛知県三河湾では細胞層が2層の「アオサ科の海藻」についても「アオサノリ」として扱っていた。
三重県の「あおさ」である「ヒトエグサ」。
漢字では「一重草」と書く。
これは一層の植物体からなるためで、裂片があり、やわらかくてぬめりがあるのが特徴。
細胞層が2層の「アオサ科」の海藻よりも食感が良いとされる。
「あおさのり」は三重県が全国の60%~70%を占める主産地で、三重県松阪市~伊勢~鳥羽~志摩~南勢~紀北までのリアス式海岸内湾や河口付近の波の穏やかな場所で養殖。
食彩品館でも南勢から志摩までの支柱式養殖「のりそだ」の風景を何回か紹介済。
↓ あおさのり養殖風景(三重県五ケ所湾)

↓ 三重県英虞湾のあおさ養殖


それでは今回、購入した愛知県田原市産の「あおさのり」の品種は何なのかというと三重県のあおさと同じ「ヒトエグサ」です。
ちなみに田原市から出荷されている「アオサ科のアナアオサ」は全国第一位で、主として「アオサ粉」として生産・出荷されています。
冒頭紹介の「青バラ干し(あおさのり)」は養殖のヒトエグサを原料として使っているので、ややこしいのですが、ヒトエグサ主産地の三重県が、方言の「あおさ」をそのまま商品名に使用しているため、ややこしいことになったというが、そのあたりの事情はここでは触れません。
それでは、購入時に「ヒトエグサ」なのか「アオサ」なのかを知るにはどうしたら良いか。
一番、確実なのは商品パッケージの原材料表示欄を見ればすぐに判明する。
また、ヒトエグサを使っている商品名には「あおさ」とひらがな表記で、アオサ科を使っている場合は「アオサ」とカタカナ表記していることが多いということも覚えておけば、商品名を見ただけでおおよそ主原材料がわかります。
★「はじめましてあおさのりです」
原材料表記を確認すると
・商品名 あおさのり
・原材料 ヒトエグサ



全国のあおさ出荷量の10%程(5~6位)と、三重県とは大きく差があるものの、愛知県のあおさ養殖の歴史は三重県同様に古く、1970年代に三重県で養殖技術が開発された後、愛知県でも導入され、現在は田原市の旧渥美町である福江湾で生産されている。
渥美半島の養殖ヒトエグサは乾燥させると他産地よりも「より青い」という評価があるようで、今回、購入した「はじめましてあおさのりです」も色が濃い。
当商品は渥美半島たはらブランド認定商品。
~渥美半島たはらブランド認定事業は、田原市の地域資源や地域特性を生かした優れた産品を、「渥美半島たはらブランド」として認定し、市内外への情報発信を行うことにより、地域経済の発展および田原市の知名度向上に寄与することを目的としています(田原市HP)~
ヒトエグサにおいてぶっちぎりの生産量を誇る三重県は歴史的に海藻類を伊勢神宮へ奉納したり、租税として収めたりする歴史があり、平安時代の延喜式には斎宮で紫菜(海苔)が供されたという記述もみられる。
旧志摩国における海苔生産は伊勢神宮への献上品・奉納品として発展し、現在につながっています。
愛知県在住としては田原市に頑張っていただき、生産拡大を願うばかり。
そのためにも消費拡大に協力しなくちゃ・・・ということで購入した次第。
***************************
◇関連記事
・2021/03/25愛知県田原産あおさ
・2020/05/25あかもく,他海藻類について
◆食彩品館.jp 海藻辞典記事
■あおさ関連商品
↓ 志摩市浜島町のあおさその他海藻

↓ 志摩高校調理部考案 あおさクッキーアイス

↓ 鳥羽産 ぎゅーとら あおさのり

↓ 志摩市大王町 あをさ

↓ 近鉄レストラン あおさラーメン

↓ ミエマンあおさしょうゆ

↓ かっぱえびせん。あおさの味噌汁味

↓ 紀北町のあおさのり(ギョルメ舎フーズ)

=====================
ところで、購入したAコープ桜町店は2021年3月26日に閉店します。
エーコープあいち桜町店(JAあいち,JA西三河Aコープ事業)2021年3月26日閉店



・3/26閉店 Aコープ桜町店
愛知県西尾市桜町5丁目18番地
℡0563-56-1141
閉店日2021/03/26
記録日2021/03/12(紹介記事3/25)
◇出店地付近の地図
================